


|
「アベノミクス」に対する経済提言
賃上げと安定した雇用の拡大で、暮らしと経済を立て直そう
「即時原発ゼロ」の実現を 日本共産党の提言
日米安保条約をなくしたらどういう展望が開かれるか:全国革新懇総会 志位委員長の記念講演
改憲派の三つの矛盾と憲法9条の生命力:5・3憲法集会 志位委員長のスピーチ
|
小池晃物語 ―小池晃さん語る 生い立ち・青春・共産党 3"社会の病気"治し、命守る 東北大学を卒業してからは、研修医として小豆沢病院(東京都板橋区)に勤務し、その後、10年余り、甲府共立病院(甲府市)、北病院(北区)、代々木病院(渋谷区)で医師として働きました。 研修医や若手医師の時代は、とにかく治療方法、薬の使い方などを走りながら勉強し、また走るという感じ。全日本民主医療機関連合会(全日本民医連)の病院なので、チーム医療、民主的集団医療をモットーにやっていますから、看護師、薬剤師、検査やX線の技師、事務のみなさんらと力を合わせて患者さんを治していくというチームの仕事には本当にやりがいを感じました。 入院できない 一方では、地域医療の現場、とくに民医連の病院で働いていると、病気だけを治していれば完結するという世界ではないということも日に日に痛感するようになりました。 さまざまな社会的問題をかかえている患者さんが来るし、救急外来などで治療にあたっていると、来たときにはすでに手の施しようのない進行したがんだったとか、長時間過密労働でまだ若いのに心臓病、脳卒中とか、そういう患者さんを何人も見ました。患者さんの背景にある経済的・社会的条件、そしてその条件をつくっている政治の貧困を常に感じながらの仕事です。 あるとき、夜間外来で診察した個人タクシーの運転手さんは、糖尿病の患者さんでした。定期的にではなく、思い出したようにときどき来る人でした。血糖値を測ったら、すごく高い。「入院したほうがいい」といったら、「先生、入院なんかとてもできない。車を買い替えたばかりで、死んだら保険金が入るから、その方が都合がいいんだ」といわれました。その言葉は、いまでも忘れられません。 脳卒中で救急病棟に運び込まれた、お年寄りの患者さんも診ました。懸命の治療で、非常に危ないところを乗り切って、やっと自宅に帰られるようになったと思ったら、家族はどうしても仕事をしなければ暮らしていけないので、昼間、面倒をみる人がいない。自宅では引き取れない、といわれました。仕方なく、いろんな病院や施設を転々としている間に、病気がまた再発し、後日、「亡くなったそうです」という連絡がありました。 毎日毎日が... これらは一つや二つのケースではありません。毎日毎日が、そんなことの連続でした。 医療・介護の現場で働いている人の多くは、日々、医療制度、介護制度、そして社会の矛盾を感じながら、悔しいけれどもがんばるということの連続じゃないでしょうか。 いまの日本の社会保障、医療、介護の仕組みそのものを変えないと、本当の意味で責任を持って患者さんの命を守ることはできません。いわば社会の病気、政治の病気を治すことで、患者さんの命を守りたいという思いがつのっていきました。 トラックバック(0)トラックバックURL: http://www.a-koike.gr.jp/admin/mt-tb.cgi/110 |
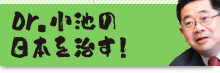 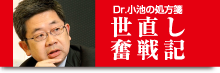 |


コメントする