


|
「アベノミクス」に対する経済提言
賃上げと安定した雇用の拡大で、暮らしと経済を立て直そう
「即時原発ゼロ」の実現を 日本共産党の提言
日米安保条約をなくしたらどういう展望が開かれるか:全国革新懇総会 志位委員長の記念講演
改憲派の三つの矛盾と憲法9条の生命力:5・3憲法集会 志位委員長のスピーチ
|
小池晃物語 ―小池晃さん語る 生い立ち・青春・共産党 2どういう医師になるか 高校時代に父の本棚で見つけた一冊の本が、医師をめざす一つのきっかけになりました。長野県・佐久総合病院の院長をしていた若月俊一さん(故人)が書いた『村で病気とたたかう』(岩波新書)という本です。 地域の農民たちと力をあわせて健康づくりをやり、村の健康状態をみんなで良くしていく実践が書かれていて、医師という仕事は地域の人々と力をあわせて健康をつくっていくものだという思いが伝わってくるものでした。 本の最後に若月さんは「医者は、単なる技術者であってはならないのではないか。...もっと『人間的』『社会的』医者であってほしいと、国民は願っているのである」と書いています。医師は、「命を守る崇高な仕事だ」という思いとともに、「学問や知識はいったい何に生かしていくべきか」と自分に問いかけました。
受験勉強の中で 日本共産党に入党したのは、大学受験に一度失敗し、予備校に通っていた19歳のときです。 予備校に共産党の支部があり、はじめに入党の話を聞いたときは「大学受験があるから合格するまで待ってほしい」といったのですが、「共産党に入り、生き方の目標を持つことで受験勉強も進む」という話をされたことをおぼえています。 そのときに共産党に出合えたことは本当に幸せでした。受験勉強だけを一生懸命やるということではなく、どういう医師になるのかについて、問題意識をしっかり持ちながら勉強することができたように思います。 「医学連」を再建 東北大学医学部に入学したのが1980年。大学時代でまず思い起こすのは、教養部時代に学費値上げ反対闘争に取り組んだことです。 学部間格差の導入がいわれて、医学部の学費はとくに大幅に値上げが計画され、僕は教養部自治会の委員長として学費値上げ反対運動に没頭しました。運動の結果、学生大会が二十数年ぶりに成立してスト権を確立し、さまざま妨害を打ち破って、教養部のストをやりきった。これは大きな体験でした。 医学部に上がってからは、医学生ゼミナールという全国の医学生の自主的なゼミナール活動で「どういう医者になるのか」という議論を夜通しやりました。大学で研究する道もあるけれども、地域医療を支える役割を果たし、病気だけではなく背景にある社会的条件、経済的条件もしっかりみることができる医師になろうじゃないか。そんな議論をしました。 在学中には勉学のかたわら、東京都中野区にあった全日本学生自治会総連合(全学連)の会館に3年間常駐し、医学生自治会の全国組織=全日本医学生自治会連合(医学連)の再建(1984年)にも取り組みました。 再建大会の最終盤は毎日激論でした。一つの全国組織を結成するというのは得がたい経験で、その医学連はいまも脈々と続いています。うれしい限りです。 トラックバック(0)トラックバックURL: http://www.a-koike.gr.jp/admin/mt-tb.cgi/109 |
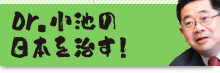 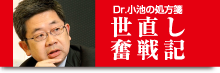 |
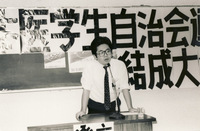

コメントする